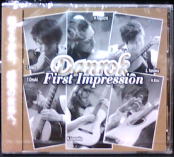4月26日(木)
こないだ、銚子にあるハーブ園の中にある雑貨店で、撮影用の器を買った。
311の地震で壊れた器は、一度には揃えられないから、
すこしずつ、購入中。
器をあれこれと、20枚ほど、仕事場に送ってもらうことにした。
ふとレジのそばにあった、ムスカリの花の球根を見て、
いつもは春にしか咲かないムスカリが
昨年は秋に狂い咲きをしたことを思い出し、
その話をレジ中にしていた。
翌日、器が宅配で送られ、箱をあけると、あのムスカリの球根がポンと
おまけに入っていた。
店長さん、ありがとう。
秋が植え時らしいので、夏が終わったら、植えよう。

今、事務所のプランタンにも今はムスカリが沢山咲いていてる。
たまたま、昨年の2月ごろだったか、
大好きな広田せい子さんのブログの中のエッセイを読んでいた時
ヒヤシンスは漢字で書くと、 “風信子” という字にくぎづけになった。
ムスカリはヒヤシンスと同じユリ科で、ムラサキヒヤシンスとも呼ばれている。
なるほどなるほど・・・
“風信子”
しかしながら、私はこれをどうしても声を出して
“かぜ・のぶこ”さんと人の名前のように呼びたくなる。
そうなると、ムスカリは人間名だと
“しかぜ・のぶこ”
“むらさきかぜ・のぶこ”
どっちかなぁ、と中年にもなって小学生のような妄想にふけってしまうのである。
もう一つ疑問が・・・
いったい誰が日本の漢字をつけるのだろう。
ムスカリにはまだ、漢字名がついていないようです。
素直に考えれば、というか、ヒヤシンスを中心に考えれば
紫風信子ですが・・・
どこにも書いてない・・・
ついでにもう一つ疑問が・・・
なぜ、小学校の理科では、ヒヤシンスを育てることになったのだろう。
いまは知らないは、いま高2の娘が小学生の時は
まだ、ヒヤシンスだったような気がする。夏はミニトマト。
沢山球根植物のあるなか、 なぜ、ヒヤシンスなのだろう。
そして、小学校の理科では、風信子という漢字は習わなかったな・・・。
リカは理科。コクゴは国語と、しないで、
ナチュラルな形で、理科の授業中に雑学的に
教えてしまう方が、授業としては面白いのに
前回の日記は女郎花。
この花の漢字は、なにかの本を読んでいて、ふり仮名をみて
スッと頭に入った。そして、女郎という言葉が引っかかって、
廓・昔の女性の立場・着物の帯の歴史・花魁・・・・と
どんどん、歴史の世界までパズルゲームのように
知りたくなる。で、結局おみなえしが咲くのみるにつけ、
なぜ、この漢字なのか、
なぜ、がつながりすぎていく。
つながる・数珠・数珠はなぜ、あのような形
だれが決めた?となぜがどんどん増える。
小さい子供が、なぜを言葉にして連発しているけれど、
大人になっても心の中はそうは変わらない
若い頃は、もっと生きていたいなんて欲は
案外ないものだが、なぜの解決をしないことがどんどん増えて
長く生きなきゃ・・・なんてそんな事を思うことがある。笑。
そして、漢字は漢字で覚えることになるから、勉強がつまんなくなるんだ
そんな気がした。